そう。
これは何回も書いているのだが。
CMSで自分のホームページをもったはいいが、どうにも使い方がわからない。
わからない、わからないといっても、このままに放置してくつもりはない。
はい。
再挑戦します。
そう。
これは何回も書いているのだが。
CMSで自分のホームページをもったはいいが、どうにも使い方がわからない。
わからない、わからないといっても、このままに放置してくつもりはない。
はい。
再挑戦します。
まだまだWORDPRESSがわかっておらず、投稿がままならない。下づくりをお願いしたデザイナーにいろいろと聞きながら作っていくつもりだったが、やはり少しは自分で勉強して基本を理解しておかなくては、どうも意図がつながらない実感があって、先へ先へと延ばしてきたが、ここに来て「書きたい」気持ちが高まって、こうしてパソコンに向かっている。向かっているのだが、これがどのように表示されうのかがわからないのだが(笑)、これもともかくやってみながら覚えていくしかないだろう。
「書きたい」というのは、「考えを整理したい」ということなのだ。漠然漫然と思いを巡らせるのではなく、言葉で現在の状態を書き出して、前に進んでいく力としたいのだ。
さて、大会の11月5日(日)までに1か月を切った。出発は11月2日ということは、残りは約20日。目標は6時間30分で完走。ということで、練習目標として6時間を設定する。キロ8分30秒のペースである。記録をつけることはしていないので、記憶となるが、これまでのマラソン参加は5回かな。最後の大会はコロナ前。20キロで膝を痛めて歩けなくなってDNF。その前年は5時間以内(多分4時間45分程度)で完走していたので、マラソン自体は多少の経験記憶をもっている。その経験からすれば、ポイントは痛み。痛みは必ず出てくる。それを我慢できる程度におさえれば、6時間前後にはゴールできる。そのためのプランを検討している。
とここまで書いてきて、次はまた明日。
前々から、岩﨑博の個人ホームページを作ってみたいと思っていた。ただし条件は自分で運営のコントロールができること。農夫が日々畑を耕すように個人ホームページを更新していきたいと思っていた。それをbloggerでやってみるか、WORDPRESSでやってみるか、大いに迷ったのだが、基本的にはWorkshopと名付けているように、個人商店として商いをしてきたいというところから、プロの手をかりてWORDPRESSとした。まずはプロにサーバー設定、ブログの移行など全体をつくっていただいたのが12月。それ以降、放置状態であったのだが、ちょうど仕事が一段落したこの連休に、ともかく自分でやってみようということで、いま、始めている。
やってみると、少しずつ、WORDPRESSとはどのような考えと仕組みでできているのかがわかってきたが、正直なところ悪戦苦闘中。しばらくは悪戦苦闘したうえで、お願いしていたプロに相談をしよう。はてさて、どうなることやらなのだが、やはり、自分でやってみないとどうにもならないのだ。
写真アップをしようとすると alt属性がないとアップできない との指示。alt属性????なんて感じでやっています。これはとりあえずの写真で、4階の私の家からみた青空と雲。


私は勝負ごとが苦手である。勝った負けたによる感情の揺れが、どうも身に合わない。1分1秒の記録を目指すのも、やはり身にあわない。スポーツはやるのも見るのも大好きだが、自分の暮らしのなかでは、ハングリーであったり、我を忘れて汗をかいたりという暑苦しい世界が苦手なのだ。人それぞれマイペースで好きにやればいい、という感覚が私の根底にある。
そんな私だからトライアスロンが身に合っていると思っている。
いつも何をやっても大きく引き離されて最後尾であるが、あまり気にせずに、マイペースで楽しんでいる。できないことはできないし、まあ「他人のことは関係ない」のだ。
それなのにスイムのタイムが気になっている。早く泳げるようになりたいと強く思っている。ランもバイクも遅くとも気にはならないのに、なぜかスイムだけはタイムが気になるのだ。
トライアスロンを始めてから、何とか100メートルを2分で泳ぐようになりたいと思った。「人生なりゆき」を信条とする私には珍しく、なぜか目標というものを設定したのだ。しかしトライアスロンを始めて13年にもなるのだが、いまは25メートルが30秒、50メートル1分10秒、100メートルで2分30秒程度か。100メートル2分は遠い世界のことなのだ。
しかし、どうしてスイムだけそう思うのか、この年齢にもなって目標を追い求める日々はどのような意味をもつのか、それはできないことを求めるストレスなのか、あるいは活力をもたらす挑戦なのか。いやいや気晴らしという説もあるぞ。
ということで、スイムを通して、いろいろと思いを巡らせてみたい。
なのであるが、スイムの話に入る前に、このブログを書き続けることについて、いまの私の気持ちを皆さんにお伝えしておきたい。
このブログはタイトルにあるように、もののはずみで、何の経験もなく「58歳でトライアスロンを始めた」メタボ親父のドキュメントとしてスタートした。私のブログがご同輩の刺激となり、トライアスロンを始めたり続けていくうえでの、いささかの参考になればありがたいとの思いがあった。トライアスロンは下手でも、下手なりの体験記が、トップアスリートのの言葉よりも凡人の苦労話が参考となることもあるだろう。そんな考えがあった。実際にこのブログから影響を受けたとの声もいただき、それはそれは大きな歓びとなった。
しかし、いまは71歳となり、トライアスロン経験も13年を重ね、いっこうに上達なく、衰えていくばかりのなかで「ベテラン」などと呼ばれて驚く事態になった。もう「始める記」ではないだろう。では「続ける記」なのか。であれば続けることの何を書いていけばいいのか。
実はそれがよくわからなくなって、ブログも休みがちとなっていた。
そんな状態が続いていくなかで、さてどうするか。
むせかえる まぶしい空へ 盆の煙
「トライアスロンを生涯スポーツとして楽しむ高齢者の心境」を綴っていきたいと思っている。トライアスロンに向かっていくなかで、高齢者にとってのスポーツの意味や楽しさを考え、書いていきたいと考えている。それがトライアスロンに限らず、何らかのスポーツを楽しむご同輩の方々にとって、いささかの楽しみとなれば、大いに嬉しい。
「実録ドキュメント」のつもりでスタートしたこのブログだが、「高齢者の生涯スポーツエッセー」としての再スタートである。
写真は5月5日の丸の内。若葉と日の光が美しかった。
再スタートの気分に似合う写真を選んだ。

昨年の12月から約半年。
ようやく「心身」が回復して自分自身を取り戻してきたように感じている。
こうしてブログに向かう時間、心の余裕もとれるようになった。
この半年を振り返れば、新年を迎えて歳を重ね、年年歳歳桜は咲き、人並みに花見にでかけ、いくつかの展覧会で絵を愛で感激に浸り、贅沢な席でラグビー観戦プラス飲み会を楽しんだが、なんともせわしなく、我が身を忘れるような日々があって、5月の連休も休んだのは一日ぐらいだっだろうか。
まずは心身の「身体」について。
12月に痔の手術で、その後約3か月は回復待ちだった。
ようやく走れるようになったと思ったら、左膝に水がたまり、屈伸もできない。
膝の水を抜きに整形外科に通って、まだ通っているのだが、これは元にもどってきた。
そうこうするうちに喉の炎症がはじまり、2週間ほどはともかく「疲れる」のがまいった。夕方には一日の疲れから、帰宅する地下鉄で一台乗り過ごしても空いてる席を探してしまうのだよ。幸いに新型コロナではなかったようで、これも気が付けば回復している。
そんななかで、手羽先の骨をかじって歯を痛めるなんてこともあった。
なかなかに大変だったのだ。
この間、仕事は新しく始まるプロジェクトがいくつかあって、それぞれに手さぐりで仕事の形をつくっていく状態でパソコンを叩きまくる毎日だったのが、進むものは進む、思うようにいかないものはいかないことがハッキリしてきて、だいぶ落ち着いた日々となってきた。ようやく「なにもジタバタしてもしょうがない」の心境となった。
さらに確定申告、決算、復興支援金の手続きと続いたのだが、これも何とかやり過ごした。
心身ともに、大変であっても、我が身を忘れても、すべては終わっていくのだ。
こうしたなかで思うのは「なかなか思うようにはいかない」という至極あたりまえのことで、この年齢になって言うようなセリフではなく、まあ、30過ぎあたりで実感するものとも思うだが、残り人生少ないこの歳になると、その状態に抵抗するのでもなく、嘆くでもなく、「仕方ない」と心に収めて一日一日を「やり過ごし」ていくと、穏やかな日がやってくるというわけだ。それで大いに満足で、その日は好きな音楽を聴いて本を読む。
そこでようやく話はトライアスロンに。
スイムはそこそこにやってきた。名倉コーチに学ぶこと多く、泳ぐということの入口にたてたような思いでいる。ポイントはフォームで、正しいフォームとは何かが、それができなくとも、理解し、それに向かうことができるようになってきた。
ただし、相変わらず遅い。今日は50メートル×4本の3セットだったのだが、1本目こそ1分3秒であったが、その後は1分5秒から10秒はかかってしまう。なんでこんなに遅いのだ。めげずにやっていくしかないなあ。
バイクは1回80キロのロングライドにでかけただけで、乗っていない。ジムで週に1回30分のエアロバイクでフォームを意識している。
ランとなると、膝を痛めてまったくの状態だ。
まずはランを回復させたいと思っている。
10キロは普通に走れる状態にもっていきたいと思っている。
話はそれからだ。
というより、ようやくこんな話ができる状態になったというほうが当たっているのかもしれない。
どこまでも 歩いていける 五月の夕陽
日差しが強くまばゆいばかりとなった。
こうした自然の変化を肌で感じるとき、トライアスロンを始めてよかったと思う。
そんな調子で、どこまでやっていけるのか。
それは自分でもわからない。
自分自身を愉しみに見ている。
写真は私のランニングコース。

ことが起こったのは3週間ほどまえ。昨年末からのリハビリもようやく回復モードになり、ランを始めていたのだが、この日は走り出して300メートルほどで、アキレス腱に違和感を覚え、アレという感じで左膝に痛みが走った。かといって走れないほどではなかったが、どこか嫌な感じが気になって走るのをやめ、ウォーキングに変えて3キロを歩いた。その日はそれで終えたのだが、翌日から膝が痛み、しゃがむことができない。
このように書いていても、なんだかよくわからない。歩きからゆっくりと走り出し、スピードをあげたわけでもない。その1週間前ほどには、ランの練習で7キロは走っていた。何かの拍子にとは思うのだが、何の拍子なのだか釈然としない。こういうときはまず「加齢かなあ」と思うようになっているが、さてそれは間違いないところとしても、それだけなのか。
そこが気になり、すぐに再生医療での膝関節医療を売りにしているクリニックをネットでみつけて行ってみた。自由診療で初心料が3,300円である。再生医療はともかくとしても、膝治療の専門家として自由診療を掲げる医師に診断をしてもらおうという気が働いた。特にこれは加齢のなのか、加齢であれば今後どのように対応していくのかを聞いてみたい気がしたのだ。
初めにこのクリニックに行く前に、提携の検査クリニックでMRIを撮影してデータを持ち込む。肝心の診断であるが「さすがにトライすロンをしているだけあって膝は若い」という。そして半月板の後ろに水がたまっている。そのあとは主にPRP-FD注射という「売り」の治療法の説明が中心となり、それはそれで勉強にはなったのだが、値段はなんと1回につき20万、3回セットで50万という。
いやいや、膝は若く、特段の変形症状などがないのであれば、普通の保険治療にしますわ。
ということで、すぐにまたネットで調べ、MRI検査のCD-Rをもって。日本橋の整形外科病院に行った。診察では半月板の一部が少しすり減っており、水がたまっているということ。すぐに水20CCを抜いてヒアルロン酸の関節注射を受けた。水を抜いたおかげでだいぶ楽になりなったが、まだしゃがむと痛い。翌週も行ってまた水を20CC抜いて、ヒアルロン酸を打った。まあ、日一日と快方に向かっている実感はあるのだが、これをきっかけに膝の衰えを強く感じ、例えば地下鉄の階段を下りる際におもわず手すりを握るなど、老化の現実をひしひしと感じている。しかしおかげざまで「若い膝」だそうだ。「これは加齢ですね」の診断もなかったぞ。(笑)どうも原因は釈然としないが、こうしたこともあるのだろう。大事ではなくてよかったと納得しよう。
このことでの改めての私の自戒教訓。
1 何かあればすぐに医者に行く。ほおっていても衰えるばかりなんだよ。
2 クリニックは都心が便利だ。家の近くは子供と年寄りで混んでいる。
3 日々少しの時間をみつけてマメにストレッチと筋トレを行うこと。
話は変わるが、確定申告で計算をしたら、昨年の医療費がなんと80万円を超えた。30万の痔の手術と30万のインプラントが含まれるのであるが、それを引いても20万程度は身体のケアに費やしていることになる。
これには呆れてなかば諦めつつも、なにが自分にできるのかといえば、煙草はやめて、酒もだいぶ減らしているし、身体も動かしている。あとはよりこまめに身体に気をつけて、何かあれば早く医者にいくことぐらいである。
桜のなかで 子供が走る 平穏無事かな
ロシアのウクライナ侵攻といった事態が生きているうちに起きるという実感はもっていなかった。
私たちの先輩はこの世を「諸行無常」と詠んだ。そんな世であればこそ、老いていく自分を静かににみつめ、毎日変わらずゆっくりと歩いていきたいと思うばかりである。
写真は私のランコースでの桜。毎年この桜を眺めて「さあ、行くぞ」という気分になっている。もちろん今年も「さあ、行くぞ」なのだ。

一晩寝て、前回のブログを読み直し、ちょっとヒトコト付け加えたくなった。よろしくお願いします。
私のトライアスロンの実力なのだが、オリンピック距離でなんとかギリギリ完走レベル。スイムで足きりは何回もあり、昨年の千葉市シティもあと100メートルほどで足切りになった。時間制限がなければなんとか完走はできるのだが、相当に下のレベルである。
ちなみにこれまでの最長大会は伊是名大会の88キロで、これも初参加はスイムで目の前50メートルででシャットアウト。2回目で時間ギリギリで完走を果たせた。
先週の土曜日にATAのラントレーニングでは、2,000メートル、1,000メートル、1,000メートルのインターバルであったのだが、2,000メートルで約14分、最後の1,000メートルで6分30秒程度であった。
スイムは25メートル28~33秒、50メートル1分~10秒、100メートルは2分20~30秒ほどもかかってしまう。
58歳ではじめたときからそうであったのだが、レベルとしては一貫してギリギリで、大会のみならず、集団トレーニングをしても、いつも最後尾、それもグループを離れての最後尾である。
トライアストンを始めたけれど、やめた方も少なくないと思う。その多くは「やってみたけどついていけない」、端的には「タイムが出ない」ことにあるかと思う。これがランであれば、一人で練習を重ねてマラソンに出ることは可能であるが、トライアスロンはなかなかそうはいかない。やはりどこかのチームかスクールのお世話になることとなり、私の場合はアスロニアにお世話になっている。
そこでトレーニングに参加したら「ついていけない」となると気持ちもなえるであろう。私の場合は「大きく遅れるが、ギリギリでついていけた」から続いてきた。「わあ、こんなにできないのだ」「もう少しできると思っていた」という根拠のない驚きはあったが、それでも辞めようとは思わなかった。
そのいちばんの理由は「私は生涯スポーツとしてトライアスロンを始めた」ためであると思っている。老いの人生を楽しむために、何か生涯スポーツを探していくなかで、たまたまトライアスロンに出会った。トライアスロンに関心があったわけでなく、熱烈ラグビーフアンであるが、トライアスロンの中継を追いかけることもなく、有名選手の名前にも関心ない。
練習で一人大きく遅れることは愉快ではない。大会で足きりになり一人荷物を片付ける情けなさはなんともやりきれない。
でも、そんなことは関係ないのだ。私が関心があるのは「私自身の生涯スポーツとしての楽しみ」であり、言葉は悪いが「人のことは関係ない」のだ。だからやってこれたと思っている。大会の足きりも、できればホノルル大会のように「足きりなし」が望ましいが、大会の事情もあろう。
そんな気分なので、これまで参加した大会の記録もつけていない。garminの時計をつけているが、それを見ながらトレーニング計画を立てるわけではない。
というわけで、前回のブログで「トレーニングを軸にした暮らしづくり」を書いたが、このトレーニングは「私の暮らし方」であり、「老人の暮らしの技術」ではあるが、「トライアスロンの記録向上、能力向上」を目指すものではない。そして、私にとってのトライアスロンの魅力とは、やはり「すべての完走者が勝者である」という文化にあると思う。トライアスロンは、このようにルーズに付き合っていくことができるのだ。
このこと伝えておきたかった。
とはいえ、そんな私でも、スイムは100メートルを約2分、ランは10キロ約6分ペースを目指している。
この目標は多くの人にとっては当たり前のレベルであり、私にとっては高いハードルであるのだが、こうした目標をもつことは、暮らしの刺激となる。
「トレーニングを軸にした暮らしづくり」とは、こうした目標設定も含め、トレーニングは心身と暮らしのいい刺激となると思っているのだ。
私自身のトライアスロンの実力を考えると、よくピーター・シェーファーの戯曲「アマデウス」を思う。神に祝福された天才モーツアルトと凡才サリエリ。神がサリエリに与えた才能とは、モーツアルトの天才をいち早く見抜く力であった。サリエリは言う。「私はすべての凡人の王である」。
私は一人の凡人として、スポーツの魅力を、トライアスロンの楽しさを語りたいと思っている。

2月16日に71歳の誕生日を迎えた。
この前のブログは1月2日の新年のご挨拶ブログ。
それ以来、何回か下書きを書いてみたのだが、どうもしっくりこないまま、アップを見送ってきた。
そんなうちに誕生日となり、いま改めてアップに向かおうとしている。
「しっくりこない」というのは、いろんな要因といろんな状態がある。
まず状態からいくと、やはり痔の手術は大きなインパクトであった。1月20日に治療完了となり、積年の不快感から逃れることはでき、トレーニングも再開して、ほぼゼロ地点にまで戻ってきている実感もあるのだが、肝心の暮らしのリズム、ペースがうまくつくれない。回復ができない。痔ではあれ、70歳過ぎての手術というのは、こんなに負担になることに驚いてもいる。
そして仕事の状態がある。日々やることに追われ、「その日にやるべきこと」が消化できず、すますべきことが先送りになって、ストレスがたまる。忙しいとは「心を亡くす」ということだそうだが、どうも仕事に追われる状態が続いている。
で、そんな要因を考えていくと、それが、どうやら「老化」に行きつくのだ。
どういうことかといえば、一日できることが確かに少なくなっているのだ。例えば以前は4つのことができていたので、その感覚で予定をたてても、こなせない。4つのところが2つ、下手をすると1つになってしまう。
テキパキとできず、活動全体が緩慢となる。そして、すぐに眠くなる。
自宅作業の日は昼食後は必ずといっていいほど眠くなり、うたたねのつもりが1時間も眠ってしまう。1時間も眠ればできることは減るだろう。出かける日は、家に戻ると疲れて、しばらくソファーで横になる。
いまテレビを見ていたら、アメリカ人や南アフリカ人は1日で9時間半も眠るそうだ。
私の夜の睡眠時間はほぼ7時間で、自然と目が覚める。そしてプラス1時間は二度寝をする。であれば、異常に睡眠に捕らわれているわけではないのだろう。
改めて整理すると、老化のために動作や作業が緩慢となり、加えて睡眠を必要とするようになり、1日でやれることが少なくなっているにもかかわらず、これまでと同様に予定を立てるのであるが、やりきれないことが多くなって暮らしのペース、リズムが崩れている、ということになるようだ。
このブログの趣旨の一つに「老いを感じる」ということがある。「老い」とはどのようなものであり、それは私の身体、思考、感性、暮らし、仕事にどのように働くのか。トライアスロンを通してそれを実感して、言葉とする。それがこのブログである。
これまで、「老いとは委縮である」と書いてきた。運動能力、感性が「委縮」している実感がある。その延長で考えれば、これは「生活の委縮」であるといえよう。
そして私が考えるのは「委縮」は避けられないものとして受け入れ、そのなかで快適に心地よく日々を過ごす方策を探し出す、あるいはそうした暮らしを創り出すことである。
さて、どうするか。
いろいろと考えてみると、直観としては「トレーニング」なのだ、これが。
委縮に抵抗して抗うわけではない。老化=委縮は自然の摂理であるのだから、それは受け入れ、あるいは全身をもって確かめ、味わうというのが私の考えである。
委縮に合わせたトレーニングを続けていくこと。
これが私が直観するこれからの暮らしの要諦、「老化の技術」である。
日々できることが少なくなっていると書いた。
要は「できない状態」に合わせた時間割の見直しである。
「老いの時間割」をまじめに考えなくてはならないようである。
そして「老いの時間割」の中心にトレーニングを据える。
これまでは暮らしのなかでトレーニングの時間を捻り出してきた。そこから、トレーニングを暮らしの軸とする。1週間の計画をトレーニングから考え始める。
「トレーニング」とは端的にはラン、スイム、そしてバイクである。
老いの暮らしのペースとリズムを創り出すとは、老いの暮らしの生活習慣を創り出すことであろう。
例えば朝の散歩。それも悪くない。あるいは朝にその日に食べる食事を準備するというのもあるかもしれない。なんだか1日が健康になるような気がする。朝の1時間をこのブログに充てるというのもあるなあ。
しかし、私の直観としては、「トレーニング」である。そう直観する背景にはこれまでの58歳からのトレーニングがある。「トレーニング」による心身への刺激が暮らしの軸になるのではないか。老人にはトレーニングが有効なのである。そのように実感している。
71歳 酷寒の誕生日に 母を思う
ここまで書いていくと、明日からでも朝ランにでかけるようであるが、そうはいかない。
私はそこまで勤勉ではない。
でも、今日はここまで書いてきて、これからの「しっくりする」暮らしへのヒントを得たようである。
幸か不幸か、仕事は現役まっただなかである。会議の設定と参加者の調整、企画書作成、交渉など、業務は日々異なり、なかなか計画はたてにくいのだが、かといって、仕事とトレーニングの両立なんて発想はない。あるいは、いうまでもなく、暮らしは仕事とトレーニングばかりではない。映画、芝居、音楽、読書、展覧会、ラグビー観戦、旅行、酒など、多くの楽しみがある。
これら総てを含め、まずトレーニングから全体の時間割を考えてみる。
71歳となり、それが「しっくりする」ための有効な方策と、改めて思うのだ。
写真は冬の青空。寒いが日差しは日々明るくなっている。遠くにスカイツリーが見える。まだ登っていないなあ。
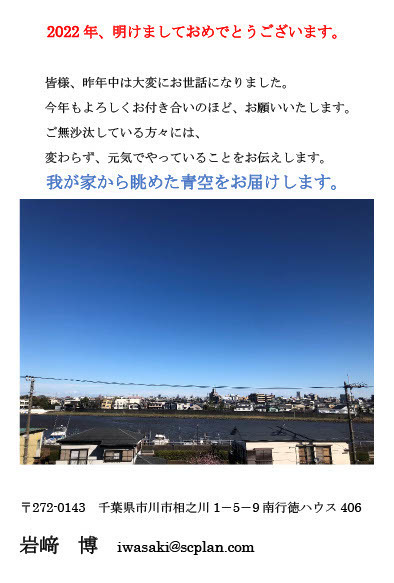
昨年を振り返ると身体の不具合に触れた内容ばかりで、70歳になるとこうしたことになるのか、と自分でもいささか驚いています。
とりわけ12月3日の痔の手術は私にとってなかなかの大ごとでした。日帰り手術で術後の回復も順調なのですが、「完治までは1か月半をみてください」とのことで、確かにいまだに練習再開を見送っている状態です。
そんななかでの2022年の初ブログ、まずは今年の予定というより「見込み」を考えてみます。
本日は2022年1月1日。手術後、今日まで運動はしてこなかった。
回復したとはいえ、肛門部にはいまだに痛みはある。
この状態からどのようにしてこれからの道筋を描いていくか。
はじめは散歩から。
昼食前に30分ほどの散歩をするのが手術前から日課だった。この散歩を手術後3日ぐらいから始め、1週間後には1時間ほどにまで延ばした。
散歩とはいえ、意識的にやっていると、これはこれでなかなか面白い。漠然と歩いているとだいたい1キロ12分。garminの腕時計を見ながらスピードを確認する。速足を意識すると30秒ほどアップする。歩くのも走るのも速さとは回転と歩幅の掛け算である。さらに回転と歩幅を意識すると30秒早くなり約11分程度となる。そこからさらに速く歩くにはどうするのか。いろいろと私なりに試してみる。さらに歩幅を広げると回転がにぶる。回転を意識すると歩幅が狭くなる。なかなか11分から縮まらない。
そこで、足のことは忘れて、胸を張り、肩の力を抜き、腕を振って腰の回転を意識するが全身の力を抜いて(ここがポイント)歩くと、これがなんと10分15秒ほどにまでなるのだ。ちょっと驚いた。人の身体とは面白い。これはランニングにも生きるはずだと頭に刻み込む。
はてさて、散歩の次はどこに向かうか。
私のイメージでは、次はストレッチ、その次はリズム、そして筋トレの順である。
なんて書くと、復帰に向けてストイックに取り組んでいるように思われるかもしれないが、そういうわけではない。
もともとメタボ老人のヘッポコトライアスロンなので、そのようには頭は回らない。
70歳にして初めて手術を受けた身体の回復というのはどのようなものなのか。そのプロセスを見つめている感覚なのだ。自分なりに動く工夫をし、ささやかな反応や結果を全身で確かめる、そんな暮らしの日々は多少の緊張を含むものであり、精神への刺激となる。しかしそのことに没入するような精神の硬直はない。私はガーデニングの趣味はないが、おそらく庭造りの楽しみに近いのではないかと想像している。あるいは「自分という畑を日々耕す農夫」に例えられるかもしれない。収穫は目標であり恵みであるのだが、それに向かう日々の手ごたえに価値があると考える。
私は「生涯スポーツ」としてトライアスロンを選び親しんでいるが、こうした「スポーツとともにある暮らし」こそが生涯スポーツの楽しみであることを実感としている。
今日は術後はじめて、約40分、ストレッチを基本にリズム運動、スクワットを行った。
ストレッチは自分なりのプログラムがある。
リズム運動といっても、好きな音楽に合わせて足を適当に踏み、屈伸する程度のことだ。
いま気に入っているのがオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥで、オリビアの明るい美声に身を委ねる。
オリビアはこちら https://www.youtube.com/watch?v=cLi8fTlDEag
18歳の私のアイドルはクリームだったけど、70歳のいまはオリビアだ!!!(笑)
クリームはこちら https://www.youtube.com/watch?v=pwDo0JUeKqM
ジャック・ブルース死亡の報に触れた時はショックだった。
スクワットはゆっくりと四股10本。
最後に、自分の手で、顔頭、腕と足をもんで刺激を入れる。
身体が伸びて、久しぶりに神経が目覚めたようで気持ちがいい。
明けまして 快晴寒風 おめでとう
今年もブログを続けていきます。よろしくお願いします。
昨年末は「我が闘病記」となったが、新年は「我が回復期」としたい。
また回復のプロセスを見つめることを通して「生涯スポーツ」への考えを深めたい。
スポーツは私たちの暮らしと社会にどのような意味をもつのか。
このブログで自らを実験台とした知見を私なりにまとめてみたいと思っています。
写真は今年の年賀状の画像です。

痔の手術を受けてから2週間が経過。術後の1週間は切除の痛みで体を動かすにも苦労した。排便が怖かったがそれがひどい痛みとはならなかったのには安堵した。そして1週間後に痛みが変化する。傷口がむき出しになったようなヒリヒリする痛みであり、ウォッシュレットで水が当たると実に痛い。これはどうしてなのか。そしていま、2週間を過ぎ、ようやくその痛みも治まりつつある。この間、傷用の軟膏を塗ったガーゼを頻繁に替える、日に2回は風呂に入るなどのケアを行う。
術後2週間はお酒NG。昨日はトライアスロンチームの忘年会があって、2週間ぶりで飲んだが、痛みが増すなどの直接的な反応は出ていない。よかった。
さて、現状報告はここまでで、前回の続きに戻る。
2020年10月、長良川トライアスロンでは、特にランで案の定、痛みがひどくなったが、どうなるものでもないので我慢をしてやり過ごした。
私の抱えたいぼ痔というのは、面白いもので、痛いとはいえ、そこで動けなくなるほどではなく、我慢すればやり過ごし、あとで風呂で温まれば、小康状態となる。レースの後も日帰り温泉に行っていたわった。
さて、レースは終えた。いよいよ手術で解消と心を決め、日帰り手術のできる病院をネットで探して2020年12月に「おおいまち消化器外科クリニック」を選んだ。選ぶにあたっては、主にホームページと医療比較サイトで検討することになるのだが、痔の日帰り手術をしっかり行っていること、ホームページでそれが説明されていること、医師の年齢、医療比較サイトで不満が少ないこと、交通の便などで総合的に判断した。
診断の結果は、内痔核が3箇所、外痔核が1か所あるとのこと。自分では外痔核の実感しかなかったので、いささか驚いた。そして私としては日帰り手術希望であったのだが、診断の結果は下痢と痔のクスリ対応となった。。
そこで考えてしまった。
クスリの対応で少し様子を見ようか。クスリで下痢がよくなれば、痔も治まるかもしれない、であれば、家の近くのほうが便利だろう。これもネットで調べると、南行徳駅前に消化器外科がある。特に悪い情報も見られない。
こちらで行ってみるか。
診断は3か所の内痔核と1か所の外痔核で同じであり、下痢と痔のクスリを出してくれる。
そこで1か月1回のペースで4カ月近く通ってみたのだが、下痢は少しは快方に向かったものの、痔のほうは小康状態でいっこうに改善しない。
診断はお腹に聴診器をあて、肛門を見て、「はい、いいですよ」で終わり。次回への予約もとらない。
手術について質問しても「ぼくはあまり勧めない」とのことで、話が先にいかない。
そこで私はこう思った。
「この医者は治す気がないな」
医者だから治す手当はする。明るく人あたりもいい。
しかし、治るまで面倒をみようといった意識、責任感がみられない。
治ったか、諦めたか、いつしか患者が来なくなれば、それで終了、ということなのだ。
そこで見切りをつけて、改めてネットに向かっていると、「患部に触らない痔の手術」という広告を見た。
詳しくはこちらで見てください。 https://okuno-y-clinic.com/
これにビビッときた。なんでもやってみたい新しもの好きの好奇心が刺激された。
手術費は約360,000円もする。しかしこれでサッパリできるのであれば、その価値はあるだろう。
思い切って電話をした。
まず、詳しい事前説明と丁寧な質疑応答がある。
カテーテルでコイルを毛細血管に埋め込み、血流を制限するというものだ。
何回も強調されたのは、必ず良くなるとは限らないということ。それはそうだろうと思う。
私の質問 「良くならない場合、その後手術することはできるか」
医師の回答「それはできます」
私の質問 「良くならない場合、その後の手術する病院を紹介するといった仕組みはあるか」
医師の回答「それはありません」
私はこれはこれで医師として誠実な対応と思う。
治す気のない医師より、治らない可能性を説明して、自分の責任を明確にする医師のほうが私は評価する。
よしやってみるか。
この訪問から1週間後にカテーテルの手術を受けた。
なお、このクリニックは値段にもかかわらず、けっこう患者が来て入て繁盛しているようだった。
年の瀬に 手術すませて 年明けへ
カテーテルの手術は約1時間。局部麻酔で意識はしっかりしている。痛みは感じないが、肛門部に温かさを感じた。
そして翌日。
劇的とは言わないまでも、7割がた良くなったように感じた。
「ほう」と思った。だんだんと快方に向かうことを大いに期待した。
しかし、そこで止まり。走ると腫れと痛みも出てしまう。
仕方ない。
改めて「おおいまち消化器外科クリニック」を再訪。
診断のうえ、日帰り手術を決定した。
今回の診断では「自然治癒はない」という。内痔核は注射、外痔核は切除で「治ります」という。
であれば「やってみましょう」となる。
手術自体は10分程度。麻酔のおかげでまったく記憶はない。
術後にクリニックで30分ほど休む。それで自分の足で歩いて帰宅する。
医師の説明では、回復には1か月半ほどかかるという。だから、手術の成果を確かめることは、まだできない。
「きれいサッパリ」を大いに期待しているが、さてどうなることか。
以上が3年にわたる私の「痔との格闘記」である。
だいぶ回り道もしたようだが、こうしたことは「仕方ない」と思うようにしている。
ここで、私の学んだ教訓をお伝えして「痔との格闘記」を終えよう。
痔の手術はお勧めである。
まだ成果を確かめるまでに至っていないが、やってよかったと思っている。
日帰りで翌日から働くことも可能であり、術後の回復も、楽ではないが、1カ月半ですむ。
診断して処方箋は出すが「治す気はない」医師がいる。
改めてこれまでの経験を振り返るとこうした医師はけっこういると思う。
そういう医師に出会ったら、すぐに医師を変えよう。
だから自分の身体は自分で考えて判断する。
医師もいろいろなのだ。
いまはネットで様々な情報を得ることができる。
改めてネット社会のありがたさを思った。
人生100年時代。これは大きくは情報産業の進展によっている。
そして情報産業は患者と医師の関係も変えていくようだ。
写真は、江戸川沿いのごみ処理工場の修理の様子。
工場全体を包み、煙突に家を貼り付ける。
すごいと思い、無心でみつめる。